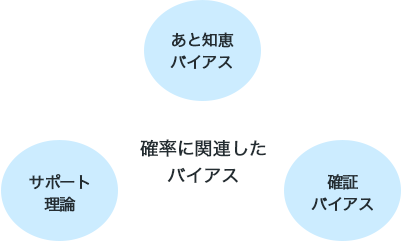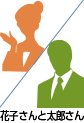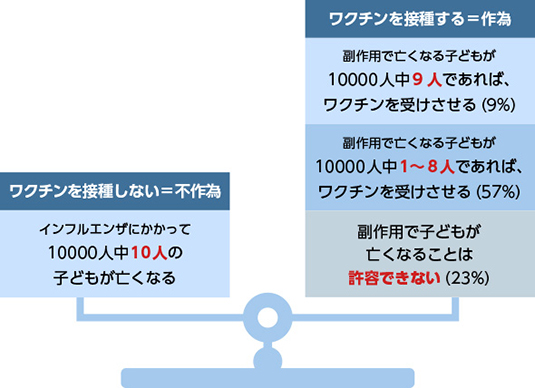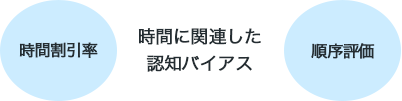ヘルスリテラシーを測る方法
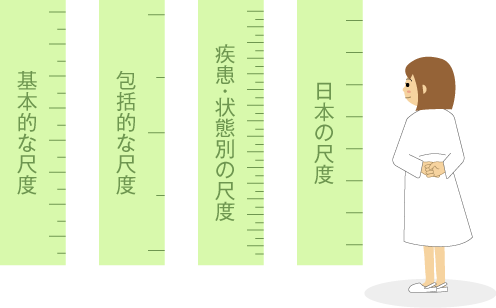
ヘルスリテラシーを測定する
最近のヘルスリテラシーの定義では、健康情報を入手、理解、評価、活用する能力で、ヘルスケア、疾病予防、ヘルスプロモーションの3つの領域で用いられるものとなっていて、多様な場面で活用する複数の能力が含まれるようになっています[1]。そしてそれに合わせた、包括的で幅広い能力を測定するものが開発されています[2]。このような現在に至るまでには、測定ツールとして多くのヘルスリテラシーの尺度が開発されていて、すでに100以上になっています。アメリカの国立医学図書館とボストン大学医学部がそれらを集めたデータベースHealth Literacy Tool Shedを作って公開しています。測定内容、質問数、測定方法、入手方法、言語などを選んで探せるようになっています。
そもそも測定の始まりは、アメリカでリテラシー(識字能力)を測定するために開発されたものです。これは読み書きに限ったものではなく、「読み書きそろばん」というように、数値を理解したり計算ができたりする数的な能力も含まれます。数的な能力は、リテラシーの一部ですが、それと区別する場合は、ニュメラシー(numeracy)と呼ばれています。ナンバー(number)とリテラシー(literacy)という2つの単語を組み合わせた造語で数に関するリテラシーを意味します。健康に関連した読解力や理解力としてのリテラシー、すなわち機能的といわれるヘルスリテラシーを測定するために開発されたのがREALM、TOFHLAなどのテストでした。これらをもとに多くの研究が実施されてきています。
ただし、これらは分量が多かったため、病院や診療所などでヘルスリテラシーの低い患者さんをその場ですぐに見つけて、その人に合わせたコミュニケーション方法を用いるという目的には使いにくいものでした。そのために、これらの短縮版が開発されたり、さらに簡略なアイスクリームの容器の栄養表示ラベルを使ったもの、1つの質問への回答で判断しようというものが開発されてきました。
さらに、糖尿病患者、がん患者向けなど、特定の健康問題に特化した尺度も開発されています。違う角度から見たものでは、インターネットの健康情報を活用できる能力を測定するeヘルスリテラシーの尺度もあります
ここでは、これらのなかから、研究でよく使われてきている基本的な尺度、すなわち機能的ヘルスリテラシーの尺度のいくつかと、包括的なヘルスリテラシーの尺度、疾患や健康問題別の尺度、日本語版が使える尺度を紹介します。
基本的なヘルスリテラシー尺度
読み書きや数的な能力である機能的なヘルスリテラシーを測定する尺度として、よく利用されてきた尺度を紹介します。
Rapid Estimate of Adult Literacy in Medicine (REALM)
125個の医学的な英単語について、適切に発音することができるかどうかをみるテスト形式の尺度です[3]。英単語を少なくした66項目短縮版(pdf)[4]、さらに短縮した8項目のREALM-R[5]、7項目REALM-SFがあります[6]。正しく発音できた英単語の数がその人の得点となり、ヘルスリテラシーを判断する指標となります。
Test of Functional Health Literacy in Adults (TOFHLA)
50問の読解力部門と17問の数的基礎力部門からなるテスト形式の尺度です。読解力部門では、病院で患者さんが実際に目にする文章などを使った穴埋め型の問題になっており、正しい回答を選択肢から選ぶものです。数的基礎力部門は、処方薬の服用方法などが書かれたラベルから必要な数的情報を扱うことができるかを確かめるものです[7]。36問の読解力部門と4問の数的基礎力部門からなる短縮版もあります[8]。サンプルをここで見ることができます。正答数に応じてヘルスリテラシーを判断します。
Newest Vital Sign (NVS)
アイスクリームの容器の栄養表示ラベルを使って対象者に読解力や解釈力、計算力を問う6つの質問からなるテスト形式の尺度です。数的能力であるニュメラシーを測定することができます。これらの質問に対する正答数が得点となりヘルスリテラシーを判断します[9]。こちらからダウンロードできます。
SILS (Single Item Literacy Screener)
現在最も簡便なもので、1つの質問で測定しようとするものです。「医者や薬局からもらう説明書やパンフレットなどの文書を読むとき誰かに助けてもらうことはどのくらいありますか」という質問に「いつも」「しばしば」「ときどき」「たまに」「ない」で回答してもらい「ない」以外の人はヘルスリテラシーに何らかの問題があると判断するものです[10]。「問診票を自分だけで書き入れる自信がどれくらいありますか」「文書を理解するのが難しく、自分の病状がわからなくて困ったことはどれくらいありますか」など、なるべく数の少ない質問で測定できないかという試みがされてきています[11]。
これらの尺度でとくに簡略なものは、診察の時にヘルスリテラシーが低い患者さんを発見するのに使えます。ヘルスリテラシーが低い患者さんは、医学的な問題の最初の兆候に気づきにくかったり、慢性の病気のために入院しやすいといったリスクを持っている可能性があります。このように健康にとってリスクのある行動をとってしまう人を早期に見つけて、わかりやすいコミュニケーションに心がけることでリスクを取り除くことが可能になります。
包括的なヘルスリテラシー尺度
予防の促進や生活の質(Quality of life, QOL)の向上を目的としたヘルスリテラシーの測定が求められるようになってきました。ヘルスリテラシーが低いことをリスクとして発見するだけでなく、ヘルスリテラシーが高いことをその人が持つ資源として測定することを目的としています。そのため、医療場面に限らない予防や健康増進などの幅広いヘルスリテラシー尺度が開発されています。ここでは、包括的な尺度として代表的な2つを紹介します。
European Health Literacy Survey Questionnaire (HLS-EU-Q47)
これはヘルスリテラシーの4つの情報に関する能力(入手、理解、評価、活用)を3つの領域(ヘルスケア、疾病予防、ヘルスプロモーション)に渡って12次元で測定する尺度で、合計で47問からできています。質問例として「喫煙、運動不足、お酒の飲みすぎなどの生活習慣が健康に悪いと理解するのは」に対して、「とても簡単」「やや簡単」「やや難しい」「とても難しい」のいずれかで回答するものです[2]。こちらで見ることが
Health Literacy Questionnaire
これはヘルスリテラシーとして独立した以下の9つの領域を設けています。
- ヘルスケア提供者に理解されサポートされている感覚
- 十分な情報を手に入れて自分の健康を管理すること
- 積極的に自分の健康を管理していること
- 健康のためのソーシャルサポート
- 健康情報の評価
- ヘルスケア提供者と積極的に関わることができること
- ヘルスケアシステムを上手に利用できること
- よい健康情報を見つけられること
- 健康情報がよく理解できて何をすべきかがわかること
一つひとつの領域に関する質問項目が用意されており、全部で44項目の質問があります。この尺度はテスト形式のものではなく、質問に対して「まったくそう思わない」「そう思わない」「そう思う」「とてもそう思う」の4件や、「できない」「とても難しい」「やや難しい」「やや簡単」「とても簡単」で回答するものです[12]。
これら2つの包括的なヘルスリテラシー尺度は他の尺度に比べて質問項目が多くなっています。そのため診察の場面で患者さんに答えてもらうには負担が大きく、利用することは難しいかもしれません。この2つの尺度は、国や地域、職場や学校といった集団のヘルスリテラシーを対象とし、個人の能力だけでなく人々を支える環境があるかを測定しているからです。そのため、環境を変えることで、人々のヘルスリテラシーを向上させて、健康やQOL(生活の質)を高める方法を考えることを目的としています。
疾患・状態別のヘルスリテラシー尺度
疾患や状態別のヘルスリテラシー尺度について紹介します。糖尿病とがんの尺度について紹介しますが、ここに挙げる以外にも、歯科、遺伝、HIV、栄養、口腔など多様な尺度があります。
Literacy Assessment for Diabetes (LAD)
糖尿病患者向けのヘルスリテラシー尺度です。これはREALMのように医療関係の単語についての発音をテストし、その語についての認知を判断するものです。提示される単語の内容が糖尿病に関するものとなっているのが特徴です[13]。
Stieglitz Informal Reading Assessment of Cancer Text (SIRACT)
これはがん患者向けの読解力を測定するテストになっています。提示される文章ががんに関する文章になっていることが特徴です[14]。
日本のヘルスリテラシー尺度
日本でもヘルスリテラシーのへの関心は高まってきており、測定するための尺度が開発されているので紹介します。
European Health Literacy Survey Questionnaire日本語版 (J-HLS-EU-Q47)
これは紹介したHLS-EU-Qの日本語版です。この尺度によって日本人のヘルスリテラシーと他国のヘルスリテラシーを比較することができるようになりました。この尺度を用いた研究では、日本のヘルスリテラシーはヨーロッパ諸国より低いという結果が出ています[15]。
機能的・伝達的/相互作用的・批判的ヘルスリテラシー尺度 (Functional, Communicative, and Critical Health Literacy, FCCHL)
これは紹介したNutbeamの3種類のヘルスリテラシーを測定する尺度です。対象者は14問の質問に対して「まったくそう思わない」「あまりそう思わない」「どちらともいえない」「ややそう思う」「とてもそう思う」の5つの選択肢で回答します。糖尿病の患者さんを対象として開発された尺度ですが[16]、後に、成人のヘルスリテラシーを測定する尺度The 14-item health literacy scale for Japanese adults (HLS-14)として利用できるようになりました[17]。
伝達的・批判的ヘルスリテラシー尺度 (Communicative and Critical Health Literacy, CCHL)
これはNutbeamの2種類のヘルスリテラシーを測定する尺度です質問項目も5項目に絞られています。回答方法はFCCHLと同じく5つの選択肢で回答します。労働者のヘルスリテラシーの測定に利用されており、患者に限らず市民に利用できる尺度です[18]。
eHealth Literacy Scale 日本語版(J-eHEALS)
これはeヘルスリテラシーを測定する尺度の日本語版です。eヘルスリテラシーとはインターネット上の健康情報を適切に検索し、評価し、活用していく能力です。今まで紹介した尺度と違ってインターネット上の健康情報に焦点を当てているところが特徴的です。成人を対象に8問の質問へ回答してもらうものです。回答方法はFCCHLと同じく5つの選択肢で回答します[19]。
Japanese Health Knowledge Test (J-HKT)
これは提示される医学関連の用語に対して対象者が一番適していると思う文章を4つの中から選ぶテスト形式の尺度です。健康に関する知識とヘルスリテラシーの関係は密接な関係にあることから知識を問うものとして開発されました。問題は15問用意されており、「腫瘍」や「エビデンス」といった言葉が問題に含まれています。これは一般の成人向けに利用されています[20]。
このように日本においても様々な用途でヘルスリテラシーの尺度が開発されています。ヘルスリテラシーを測定する際には、自分が測定したいヘルスリテラシーの定義と内容を明確にすることが大切です。それを測定できる尺度が日本にあればそれを利用すれば良いでしょう。しかし海外にあって日本に無いものや、海外にも日本にも無いものは新しく尺度を開発する必要があります。
文献
[1] Sørensen K, et al. Consortium Health Literacy Project European. Health literacy and public health: a systematic review and integration of definitions and models. BMC Public Health. Jan 25;12:80, 2012.
[2] Sørensen K, et al. Measuring health literacy in populations: illuminating the design and development process of the European Health Literacy Survey Questionnaire (HLS-EU-Q). BMC Public Health 2013 13:948.
[3] Davis TC, Crouch M, Wills G, Abdehou D. Rapid assessment of literacy levels of adult primary care patients. Fam Med 1991;23: 433e55.
[4] Davis TC, Long SW, Jackson RH, Mayeaux EJ, George RB, Murphy PW, et al. Rapid estimate of adult literacy in medicine: a shortened screening instrument. Fam Med 1993;25:391e5.
[5] Bass PF 3rd, Wilson JF, Griffith CH. A shortened instrument for literacy screening. J Gen Intern Med. 2003 Dec;18(12):1036-8.
[6] Arozullah AM, Yarnold PR, Bennett CL, et al. Development and validation of a short-form, rapid estimate of adult literacy in medicine. Med Care 2007 November;45(11):1026-33.
[7] Parker RM, Baker DW, Williams MV, Nurss JR. The test of functional health literacy in adults: a new instrument for measuring patients' literacy skills. J Gen Intern Med 1995;10:537e41.
[8] Baker DW, Williams MV, Parker RM, Gazmararian JA, Nurss J. Development of a brief test to measure functional health literacy. Patient Educ Couns 1999;38:33e42.
[9] Weiss BD, Mays MZ, Martz W, Casto KM, DeWalt DA, Pignone MP, et al. Quick assessment of literacy in primary care: the Newest Vital Sign. Ann Fam Med 2005;3:514e22.
[10] Morris NS, MacLean CD, Chew LD, Littenberg B: The Single Item Literacy Screener: evaluation of a brief instrument to identify limited reading ability. BMC Fam Pract 2006;7:21.
[11] Chew LD, Bradley KA, Boyko EJ: Brief questions to identify patients with inadequate health literacy. Fam Med 2004, 36(8):588-594.
[12] Osborne, R. H., Batterham, R. W., Elsworth, G. R., Hawkins, M., & Buchbinder, R. (2013). The grounded psychometric development and initial validation of the Health Literacy Questionnaire (HLQ). BMC Public Health, 13, 658.
[13] Nakayama K., Osaka W., Togari T., Ishikawa H., Yonekura Y., Sekido A., Matsumoto M. Comprehensive health literacy in Japan is lower than in Europe: a validated Japanese-language assessment of health literacy. BMC Public Health. 2015; 15(1): 505.
[14] Ishikawa H, Takeuchi T, Yano E: Measuring functional, communicative, and critical health literacy among diabetic patients. Diabetes Care 2008, 31(5):874-879.
[15] Suka M., Odajima T., Kasai M., Igarashi A., Ishikawa H., Kusama M., Nakayama T., Sumitani M., Sugimori H. The 14-item health literacy scale for Japanese adults (HLS-14). Environmental Health and Preventive Medicine. 2013; 18(5): 407-415.
[16] Ishikawa H., Nomura K., Sato M., Yano E. Developing a measure of communicative and critical health literacy; a pilot study of Japanese office workers. Health Promotion International 2008; 23(3): 269-274.
[17] Mitsutake S, Shibata A, Ishii K, Okazaki K, Oka K: Developing Japanese version of the eHealth Literacy Scale (eHEALS). Nihon Koshu Eisei Zasshi 2011, 58(5):361-371.
[18] Tokuda Y, Okubo T, Yanai H, Doba N, Paasche-Orlow MK. (2010), Development and validation of a 15-item Japanese Health Knowledge Test. J Epidemiol., 20(4):319-28.
[19] Nath CR, Sylvester ST, Yasek V, Gunel E. Development and validation of a literacy assessment tool for persons with diabetes. Diabetes Educ. 2001;27(6):857-64.
[20] Agre, P, Steiglitz, E, Milstein, G (2006). The case for development of a new test of health literacy. Oncology Nursing Forum, 33(2): 283-89.