このサイトについて
健康情報はインターネットの時代へ
健康や医療についての情報は、インターネットで簡単に手に入れられるようになりました。厚生労働省の2014年の調査では、健康情報の入手先として、テレビ・ラジオ(77.5%)、インターネット(74.6%)、新聞(60.0%)で、インターネットはテレビ・ラジオに近く、新聞よりも多くなっています。総務省「通信利用動向調査」 (2020年)によると、インターネットの利用割合は、6-12歳で80.7%、13-59歳はおよそ95%以上で、60歳代で82.7%、70歳代で59.6%、80歳代で25.6%となっています。また、ソーシャルメディア(SNS)の利用割合は、6-12歳で37.6%%、13-49歳はおよそ8割以上で、50歳代で70.4%、60歳代で60.6%、70歳代で47.5%、80歳代で46.7%と70歳以上でも5割近くになっています。世界中で増加するTwitter、Facebookなどのソーシャルメディアの利用で、情報が共有され、それに基づいて、自分の症状をチェックしたり、治療やケア、検査や予防接種を選んだりすることもあります。
世界でのヘルスリテラシーへの注目
このような動きに伴って、WHO(世界保健機構)や欧米での健康政策では、健康や医療の情報を"入手、理解、評価、活用”することによって、生活の質(QOL)の維持・向上のために適切な意思決定ができる能力、すなわちヘルスリテラシーが中心課題となってきています。この2010年には、アメリカ厚生省は2010年にヘルスリテラシー向上のための国民アクションプラン(National Action Plan to Improve Health Literacy)を発表しました。すべての人が、健康情報を得た意思決定(informed decisions)をする権利を持ち、保健医療サービスは、誰にも"わかりやすく"提供されなければならないというものです。ヘルスリテラシーが低いことがもたらす影響については、この20年以上、アメリカを中心として多く研究されてきました。健康状態が良くないことはもちろん、自己管理のスキルが低い、救急医療サービスを利用しやすい、入院率が高い、療養上の説明や指導を理解できない、検診受診率が低い、治療が遅れたり、治療ミスに結びつきやすいことなどがあげられています。
アメリカは多民族国家と受け取られやすいですが、白人が77.9%(2012)を占めていて、ヘルスリテラシーの低い人の多数はその人たちです。学歴とその高さは必ずしも関係しないという議論もあります。それよりむしろ、身近に健康問題を持った人が多くいて、家族や友人で一緒にその経験を共有した人のほうがあるかもしれません。社会経済的な階層が高い人であっても健康や医療の情報を理解し、意思決定するには困難を伴うことが報告されています。たとえば、手術について、「生存率95%」と伝えるのと「死亡率5%」と伝えるのではどう印象が違うでしょうか。まったく同じ情報なのに言い方の違いで結果が違ってくることは、患者のみならず医師でも起こることが知られています。
日本におけるヘルスリテラシーの紹介とその向上を目指して
では、日本もアメリカをまったく同じ状況でしょうか。確かに利用率は高いですが、そこで信頼できる情報にうまく出会えているでしょうか。ネットで検索して上位に出てくるサイトはどうでしょう。商品を買わされそうなサイトがいかに多いことか。アメリカでは、厚生省を中心として、国民向けに信頼できる情報をたくさん発信しています。他方、日本では、国の機関が出している健康情報はわかりやすさも含めてかなり劣るように見えるのが現状です。情報がないなら、ますますヘルスリテラシーが大切になるのではないでしょうか。アメリカと比べて日本では、国民皆保険で好きな病院にいつでも受診が可能なので、医療者からもっと情報を得ればよいのかもしれません。しかし、そこで誰もが納得いくまでコミュニケーションが取れているでしょうか。
また、闘病記や闘病ブログもたくさん書かれています。それらをうまく活用するというヘルスリテラシーについても一緒に考えてみましょう。
このサイトでは、世界で注目されるヘルスリテラシーのことについて紹介し、そのことによりその向上を目指して作成しました。また、欧米の健康情報サイトを見ていると、多くのサイトで、情報の見方、活用のしかたについての解説がついています。しかし、日本の同様のサイトでは、そのような解説はほとんどないように思います。したがって、多くのサイトで、このサイトにリンクしてもらい、活用してもらえればと思います。
サイト作成のためには、欧米でのこれまでの研究動向などを調べる活動が必要でした。ヘルスリテラシーに関する文献を読み、議論し、サイトを作成する仲間として、聖路加国際大学(旧聖路加看護大学)と東京大学医学系研究科健康社会学分野の修了生を中心に作成しました。このようなサイトを作る着想は、2005年ぐらいから始まっていて、当時まだ院生だった人はもう立派な社会人です。 しかし、まだまだ不足している内容もあって、新たなコンテンツを作成、追加しています。また、内容がわかりにくい点も多々あると思いますので、コメント欄にご意見いただければ幸いです。ヘルスリテラシーの向上を確認するには、それを測定する必要があるのですが、世界的にもまだ不十分で、今後の研究に期待されている状況です。それに関してもご意見いただければと思います。更新情報については、更新ブログのほうで提供していきますので、サイトの変化の様子については、そちらもご覧ください。
公開2010年11月11日 最終更新2022年4月30日
サイトの企画・運営・編集
中山和弘(聖路加国際大学大学院看護学研究科 看護情報学)分担執筆(50音順)
宇城 令(愛知県立大学 看護管理学)大坂和可子(慶應義塾大学 成人看護学)
大宮朋子(筑波大学 公衆衛生看護学)
佐藤繭子(三井物産)
瀬戸山陽子(東京医科大学 教育IRセンター)
田口良子(鎌倉女子大学家政学部管理栄養学科)
戸ヶ里泰典(放送大学教養学部)
谷口絵里奈(東京大学医学部附属病院)
檀谷ひとみ(聖路加国際大学大学院看護学研究科 看護情報学)
中山和弘(聖路加国際大学大学院看護学研究科 看護情報学)
松本真欣(ユニバーサルビジネスソリューションズ)
的場智子(東洋大学 ライフデザイン学部生活支援学科)
米倉佑貴(聖路加国際大学大学院看護学研究科 看護情報学)
吉川真祐子(日本メドトロニック株式会社)
このサイトのリンクについて
健康を決める力へのリンクはご自由にどうぞ。次のリンクバナーをよろしければご利用ください。
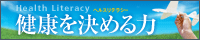
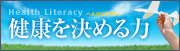
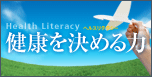
サイト作成のための研究助成金
なお、本サイトは、以下の次の日本学術振興会(文部科学省)の研究助成金によって制作しています。・基盤研究(B)(一般)「ヘルスリテラシーとストレス対処力の形成により生涯学び成長する介入モデルの開発」(研究代表者中山和弘、平成28~令和2年)研究課題番号16H05569
・挑戦的萌芽研究「患者がエビデンスとナラティブをつないで意思決定できるディシジョン・エイドの開発」(研究代表者中山和弘、平成25~26年度)研究課題番号25670928
・基盤研究(B)(一般)「ヘルスリテラシー不足の患者・家族・市民を発見・支援する看護学習コンテンツ開発」(研究代表者中山和弘、平成23~26年)研究課題番号23390497
・基盤研究(B)(一般)「インターネット情報に翻弄される患者、家族を支援する看護職のためのeラーニング開発」(研究代表者中山和弘、平成18~22年)課題番号19390552
・聖路加看護大学が21世紀COEプログラム(21世紀センターオブエクセレンス)「市民主導型の健康生成をめざす看護系形成拠点」研究補助金(平成16年~平成20年)
・基盤研究(A)(一般)「患者と医療者が分かり合えるがんコミュニケーション促進モデルの開発と有用性検証」 (研究代表者小松浩子、平成18~22年)課題番号19209066





