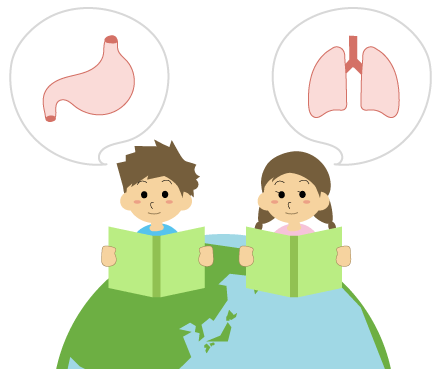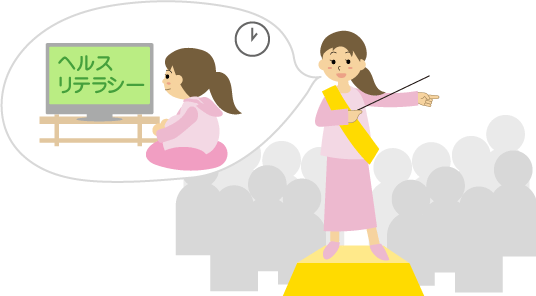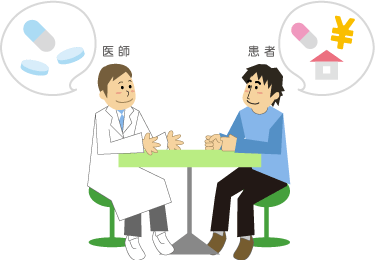「Webコミュニティのサポート機能」
インターネット上では単にコミュニケーションをとるだけでなく、同じような悩みを抱えた人が集い、そこにコミュニティ(同じ目的や価値観を持った人々の集まり)ができるという現象が見られています。
コミュニティの中では、ある参加者が相談したことに他者がアドバイスをしたり、誰にも言えない悩みを打ち明けてそれを受け止めてもらったりということが日常的に行われています。
このページでは、このような、人をサポートする機能を持つインターネット上のコミュニティ(以下、Webコミュニティ)について扱います。
Webコミュニティで得られるサポート
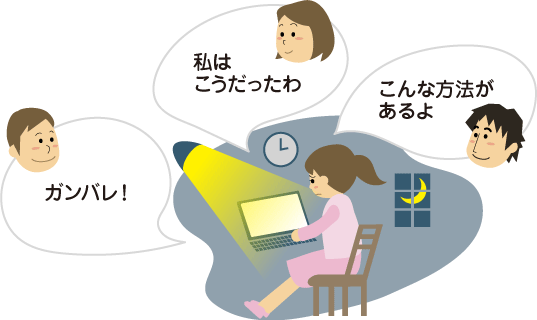
Webコミュニティで得られるサポートには、いくつかの種類があります。
情報的サポート
まずは、情報を得られるというものです。これは「情報的サポート」と呼ばれ、何かわからないことがあった時に、既に経験している人が情報を提供してくれるというものです。情緒的サポート
次に、辛い経験をしたときなどに、励ましてくれたり慰めてくれたりするサポートもあります。これは「情緒的サポート」といわれます。自分だけではないと思える
病気など必ずしもみんなが経験するわけではないことを経験すると、なぜ自分だけがこんな目に合わなければいけないのか、なぜ自分だけつらい思いをしなくてはいけないのかと思います。それでも、同じような経験をしている人がいると、自分だけではない、自分は特殊な人ではない、同じ経験をすれば誰もがそう思うのだと、安心する気持ちを持てるようになります。自分自身についての振り返り
さらに、他の人が書き込んでいる内容を読んで、自分自身の行動や思いについて振り返ったり、見つめ直したりできるという機能もあります。他の人をモデルにする
他にも、他の人がどうしているかを知ることで、その人を自分自身の生き方や生活の仕方のモデルにする(モデリング、観察学習などといいます)といった場合もあります。例えば、同じ病気を抱えた人が集うWebコミュニティでは、医師への質問の仕方や、ふだんの気持ちの持ち方など、当事者ならではの体験知がその場で共有されています。医師との関係がうまくいかないことに悩んでいた人がコミュニティを訪れて、他の人が医師にどのように自分の思いを伝えていたかを知り、その伝え方や準備の仕方を真似してみることで、自分と医師の関係もうまくいくようになるということがあります。同じ体験を持つ人が集うWebコミュニティでは、このようにロールモデル(お手本となる人物)を探すことが可能です。人の役に立つことで癒される
また、興味深いことに、Webコミュニティ上で誰かの質問に回答してあげたり、誰かを励ましたりして自分が他の人の役に立つことが、自分の癒しにつながること(ヘルパーセラピー効果といいます)があります。これもWebコミュニティで見られるサポートのひとつです。これらのさまざまなサポートは、インターネットが普及してから新しく出てきたサポートではありません。これまで顔と顔を合わせた患者会などの対面のコミュニティでも、同じようなサポートが見られると報告されてきました。
もちろんそれも貴重なのです。ただ、対面のコミュニティは特定の時間にそこにいなくてはいけないという物理的な制約があります。また、素顔を出して話をしなくてはいけないため、心理的な負担もあるでしょう。
Webコミュニティでは、匿名でもいいですし、24時間いつでも使えるため、そのような負担が少ないというメリットがあります。その一方で、匿名だと、やり取りしている相手が誰だかわからないことによる信頼性の低さということが、デメリットとして挙げられるかもしれません。
どんなものにもメリット、デメリットがあるのは当然です。
Webコミュニティは、選択肢の一つではありますが、オールマイティではありません。
体験者から話を聞きたいと思った時、自分にとってのメリット・デメリットをよく考えて、対面コミュニティとWebコミュニティをうまく使い分けられれば良いと思われます。
サポートが得られるWebコミュニティの種類
Webコミュニティには様々な種類がありますが、現在はソーシャルメディアを活用したコミュニティが中心となっています。
ソーシャルメディアには、インターネット上で社会関係を築くメディアで、従来から使われてきた掲示板をはじめとして、FacebookなどのSocial Networking Service(SNS)や、Twitterなどのマイクロブログ、個人のブログ、動画投稿サイト、Q&Aサイト、口コミサイトなど、多様な形があります。基本的にどの種類のWebコミュニティでも、その中で人と人との対話があり社会関係が築かれるので、その中でのサポートのやりとりが生じます。
しかし、そのサポートがソーシャルメディアの種類を超えて同じかというと、そうではなさそうです。
例えばTwitterなどは匿名性が高く、勝手に相手をフォローすることができますが、Facebookなどは実名で、友達になって相手の投稿を見るには通常お互いの承認が必要になります。匿名性の高いTwitterでは、自分の素性を明かさずに話ができるという気軽さがある一方で、相手の素性もわからないので、情報の信頼性を確かめることも難しくなるかもしれません。
他方で、Facebookは原則的に実名登録で、もともと対面で知り合いの人がつながる場合が多いので、どこの誰さんが何を言っているということが分かり、情報の信頼性は上がるかもしれません。しかし、例えば自分の病気のことを周囲に打ち明けていない場合は、Facebookには書き込みをしづらいという状況も考えられます。
コミュニティをうまく使いこなすために

このようにWebコミュニティには様々な種類があり、それぞれに特徴があります。また対面のコミュニティとWebコミュニティでもそれぞれにメリット・デメリットがありそうです。
では、これらをうまく使いこなすにはどうしたらいいでしょうか。
それには、まず体験者の人に何を期待しているのか、何を求めてコミュニティを利用しようとしているのかを明らかにしておくといいと思います。使い始めてから分かることももちろんあります。
しかし、コミュニティの中には非常に多様な人が人間関係を築いて対話を行っているため、それに飲み込まれたり、多くの情報を取捨選択できずに翻弄されてしまうと、自分の目的が果たせなかったりする危険性もあるでしょう。
また、これはWebコミュニティについてですが、やはり対面のコミュニティに比べると手軽であるために、ここでは膨大な量の情報が飛び交います。それらは、正しいという保証がないものもありますし、自分の場合に当てはまらないこともあります。匿名性の高いコミュニティでは、医療者を名乗っていても、本当は医療者ではないという場合も、もしかしたらあるかもしれません。
そのような大量の情報が飛び交う中、情報を見極めて、うまくWebコミュニティを使いこなすには、やはり情報にアクセスして、理解し、それを活用する能力であるヘルスリテラシーが求められます。自分がその情報の真偽を確かめるのはもちろんですが、わからなければ他の情報源のものと見比べたり、主治医や信頼できる周りの人に尋ねたりするのもいいでしょう。
Webコミュニティは、多様なサポートが得られて気軽に使える資源と言えるので、それを上手に使いこなすために、ヘルスリテラシーを意識しながら使えるとよいと思います。
(瀬戸山陽子、中山和弘)
文献
[1]Setoyama, Y., Yamazaki, Y., & Nakayama, K. (2011). Comparing support to breast cancer patients from online communities and face-to-face support groups. Patient Educ Counseling, 85(2), e95-100.